|
|||||||||||||
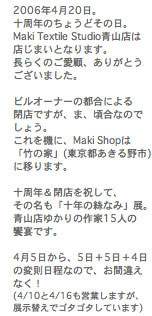 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
|
じゅうねんのいとなみ
2006年4/5(水)〜4/20(木) Maki Textile Studio Aoyama, Tokyo |
|||||||||||||
| ●その三「そして竹林」 4/17(月)ー4/20(木) Special Shawl 青山10周年記念ストール タッサーシルク100% Special Gift もれなくコースターをプレゼント。 (新井淳一氏提供の布による) Special Price Maki布がちょっとお買い得♪ Fukubiki すなわち福引き。 景品はMaki布とか、竹林ランチ券とか… Happy Point Maki ポイントを通常の二倍。 (店がなくなっても竹林で使える!) Maapai ちょっと気楽な綿麻の真南風ブラウス。 |
|||||||||||||
| ●その一「布と衣」 4/5(水)ー4/9(日) 新井淳一の布 安藤明子の衣 石垣昭子の布 石田加奈のバティック ニルー・クマールの刺し子 真木香の布 真砂三千代の衣 |
●その二「木と器」 4/11(火)ー4/15(土) 赤木明登の茶道具 黒田泰蔵の白磁 斉藤衛の家具 遠見和之の紙 中村好文の道具 真木雅子のバスケタリー 三谷龍二の木器 山口和宏の木器 |
||||||||||||
| 中村好文の道具 当スタジオお抱え建築家・中村好文氏。 02年秋に家具展を開催している。 今回はスツール(椅子)と針箱の出品。 上写真はスツール。 大人も子供も使えるよう、低めのものを新たにデザイン。高さは35cmほど。 座面は、四角、丸、三角の三種で、各二脚。 綿×タッサーシルクのMaki布が張られていて、色は白、黒、紺、茶。 価格:未定。 針箱は02年の家具展と同じもの。 |
 |
||||
 |
|||||
ウール楊柳 下の三点は「筒織」で、円筒形をしている。 ジャカード水玉 素材は主に綿×ウール。 *** 写真上 *** 写真下
三谷龍二の木器
先日青山店で展示会を開いてくれた三谷龍二氏。
今回は新しく作った器を披露してくれる。
名づけて「ラウンド・ボックス」。
和菓子などをちょっと容れる箱を作ってみたいと前々から考えていた三谷氏。
今回の展示会のことで真木千秋と相談しているうちに、それでは風呂敷ともども作ってみようという話になる。
そして生まれたのが、この器。
一塊の木から、蓋と身をくりぬいて作られている。
焼き菓子を入れてお手持ちしたり、チーズやサンドイッチを入れてピクニックに出かけたり、あるいは裁縫箱に使ったり。
(三谷氏いわく、ご飯など湿気の多いものは推奨できないとのこと)
大小2サイズ。
大・径21cm、サクラ、3万8千円。
小・径15cm、ナラ、2万3千円。
風呂敷は別売で、60cm角(11,000-12,000)と65cm角(14,000-15,000)。
ワヒッド、Mix Weaveなどの布を使い、ビーディングを施して作成。
グンディ(くるみボタン)付き。
三谷氏在廊:4月13日(木)、4月20日(木)



新井淳一の布 II
今回出品される新井氏の布は50点ほど。
いずれも2003年の新井淳一展ではご紹介しなかった布だ。
その多くは反物。
中には、あらかじめ当スタジオで裁断し、マフラーとしてすぐに使えるものもある。
そのうち幾点かをご紹介しよう。
いずれも三千円前後でお求めやすい。
上から順に;
バスケット織り
ジャカード格子
ジャカード波形
ジャカード水玉ボーダー
以上は「その一(4/5-4/9)」出品。
また「その三(4/17-4/20)」ご来店のみなさんにはもれなく新井氏の布によるコースター(二枚組)を進呈する予定。
現在スタジオではその作成に大わらわである。
新井淳一氏在廊予定:4月20日





石田加奈のバティック
ジャワ島チレボンに工房を持ち、バティックをつくり続けている石田加奈さん。
京都市内にスタジオ+Shopのisis(イシス)がある。
Maki青山店での展示会は2003年の夏。
バティックというのはロウを置いて染めるロウケツ染めだ。
写真上はチレボン工房、最近の風景。
毎年3〜4度、出かけるのだそうだ。
今回は手描きの綿サロンおよびカインパンジャンを十数枚出品。
サロンというのは下写真に見るような、筒型の衣。
カインパンジャンというのは、長い一枚布。
(なお写真と出品作は無関係)
そのほか、もう少し求め易い、チャップ、スレンダー、風呂敷も出品。
チャップというのは、バティックではなくて型押しのサロン。一万円くらい。
スレンダーというのは、古布を模した幅広のストール。
石田加奈さん在廊日は、4月*日と4月20日。


真木香の布
テキスタイルデザイナーとしてMakiを支えてきた真木香。
現在は山梨の八ヶ岳山麓に「蕪の森スタジオ」を構え奮闘中。(HPはこちら)
今回は二種類の布を出品。
「つつみ布」、すなわち風呂敷である。
二枚重ねで、上布は糸染めによる平織シルク。下布はタッサーシルク。
写真は藍系(藍染め)だが、他にグレー系(くるみ等)、黒系(ザクロ等)、黄系(フクギ等)がある。
サイズは75cm角と60cm角(黄系)
6点出品。
「遊び布」、すなわち細幅反物。
日中印など様々なシルクを使った絹100%で、滑らかな凹凸(テクスチャー)がある。
自由な長さに切って、インテリアに使ったり、首に巻いたり…。
10cm幅。
写真は生成と、黒系(カテキュー)。
ほかに藍系等も製作中。
在廊日は、4月5日&4月20日。


遠見和之の紙
能登輪島の紙師、遠見和之。
2001年に展示会をお願いしているので、まずそちらをご覧いただきたい。
写真は「紙の灯り」。
竹の枝と楮(こうぞ)で出来ている。
楮は純白ではなく、栗のイガでほのかに染めてある。(栗のイガは布にも使う染料で、きれいな茶色を染める)
これは径25cm、高さ55cmで、3万5千円。
ほかにやや小振りの灯りが二点ほど出品される。
そして紙が数種。
杉皮で漉いた紙と、楮の紙。
杉皮の紙は、さらしの程度によって、茶色からベージュ、黄色まで。
楮の紙は、藍や栗イガで染めてある。
62cm×98cm。500円

安藤明子の衣
岐阜・多治見、ギャルリ百草(ももぐさ)の安藤明子さん。
直線裁ちによる和の衣づくりで知られる。
今回はMakiの織り出し布を使ったサロン(腰巻)を七点、そして上衣を三点ほど出品。
また3月31日に出版される『安藤明子の衣生活』(主婦と生活社)も早速ご紹介。様々な作品のほか、サロンの巻き方などを収録。

サロンは三タイプ。
いずれもラオスの絹地(手紡ぎ手織り・草木染め)とMaki布。
裏地のあるものはリバーシブル。

袋サロン
内側は綿。スソを縫い閉じ。
Maki布は「ウネ」と「しゅくしゅく」。
39,900円
二つ折サロン
内側は白地の綿でスソの縫い閉じなし。
Maki布は藍生葉入りの「バーク」。
価格未定。

単(ひとえ)サロン
Maki布は「帯」。
47,250円


上衣は二タイプ。
いずれも膝下までの長さで、脇にスリット入り。
布は「Mix Weave」
価格未定
返し衿上衣
布は「うね」絹×麻
81,900円
山口和宏の木器
福岡在住の木工作家、山口和宏さん。
04年の6月に展示会をお願いしている。
この人と作品については、その際の(我ながら素晴らしい)紹介記事があるので、まずはご覧頂きたい。
氏の木器は、三谷龍二作品ともども、当家の食卓には欠かせない存在である。
写真上は15cm径の丸皿。材は山桜。(5,040円)
写真下は15cm×21cmのトレー。クルミ材。(6,825円)
ともにノミで仕上げ、クルミ油を施している。
その他、細長い皿、角皿、カッティングボードなど、40〜50点が出品される。
材は、ナラ、山桜、クルミなど。
山口さんに会いたい人は、4月20日に来店されるとよかろう。
しかし、作品が欲しい人は、「その二・木と器」期間、すなわち4月11日〜15日の間に来ること。


| ニルー・クマールの刺し子 Makiのパートナー、ニルー・クマール。 彼女との出会いから現在のMaki Textileがあることは、拙著でも述べた通り。 デリー在住のテキスタイル・デザイナーで、真木千秋とはほとんど姉妹のような関係。 青山店では01年7月に展示会を催している。 インドという地の利を生かして、様々なテキスタイルをクリエートしている。 今回の出品は「カンタ」。 これは日本の刺し子に相当するもので、インド庶民の手業に発するものだ。 古布にチクチクと糸を刺す。 それによって、布が強くなるとともに、新しい素材感が生まれる。 そして糸目の模様が楽しめる。 ニルーがカンタに取り組み始めたのは、今から十年ほど前のこと。 一部は先の青山店展示会にも出品され、好評を博している。 ニルーのカンタは、素材として、古いシルクのサリーを使う。 裏地をつけ、パッチワークにするなど工夫を凝らす。 古布の柄によって刺し方も異なり、直線刺しであったり、丸かったり。 ものによっては、一点仕上げるのに半年を要したりするという。 その細かな仕事は驚嘆に値する。 (それゆえ価格も相応である。) 作品は長方形の一枚の布。 柔らかで身に添いやすいので、ショールとして使える。 また、インテリアにしても存在感がある。 今回は十点ほどの出品。 |
 |
||||
 |
|||||
 |
|||||
| 新井淳一の布 「アライ・ラマ」の異名をとる、群馬・桐生のテキスタイルプランナー、新井淳一氏。 今日(2/23)、屋敷を訪ねたのであるが、開口一番、「今回の催しはきっと今までのご愛顧に感謝するという趣旨だろうから、ぱるば法師にちょっと相談しようと思ってね」とのたまふ。 私と真木千秋を伴い、さっそく布の宝庫へ(写真上)。 ここは新井氏の家業、かつての新金織物の機場である。広さ85坪で織機が25台ほど入っていた。 今は倉庫となって、氏のクリエートした布々が山と積まれている。 ほとんど親みたいな新井氏、Makiの行く末について文字通り親身になって心配してくれる。 「御来展のみなさんにもれなく新井淳一の布を差し上げる、というのはどうだい」とアライ・ラマ聖下。 ぱるば法師も、それは面白い!と賛同。 そこで奥から引っ張り出して来たのが、この一反。(写真中) 新井氏の名品「ジャカード梨地」だ。 黒地の中から、うたかたのごとくフッと紋が浮き出る。 通常ジャカード織というのは、色を違えて紋様を織り出すものだ。 しかしこの作は、黒一色の中でテクスチャーが浮かび上がるという革新的なもの。 コムデギャルソンのコート地として1980年パリコレに出品され、世界の注目を浴びる。 ウール×ノイル絹×綿で、変わり魚子(ななこ)という技法を幾つも使っている。 真木千秋も大好きな生地で、「これを切っちゃうの、もったいな〜い!」と言うのであるが、これを切ってコースターを作り、ご来場の皆さんに差し上げようというのだ!! 「せっかくだから日替わりにしようか」と張り切る新井氏。 たとえば、上写真で二人が手にしている生地。 表の模様は四角で、裏は三角。 これをコースターにしても面白い。 さらに二人の夢は荒れ野を駆けめぐる。 五十種にのぼる白や生成の生地を目にした真木千秋にインスピレーションが…。(写真下) これだけで展示会をしたい! 他に類を見ない白地のコレクションで、ちょっと手を加えるだけで様々に生きてくる。 実は現在、五日市スタジオの敷地内にギャラリーを建設する計画が粛々と進行中。 母屋や庭も合わせ青山より遙かに大きなスペースが使えるので、新井氏によるワークショップも交えたダイナミックな展示会を是非この秋に! …ということまで決するのであった。 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
| 赤木明登の茶箱 輪島の塗師・赤木明登。 彼には97年11月に展示会をお願いしている。 「十年の絲なみ・其の二・木と器」(4/11-4/15)では、「旅の茶箱」を出展してくれるそうだ。 昨日2月10日、青山店に来店し、真木千秋とその打合せ。 仕覆(しふく)の布を真木千秋が担当するのである。 仕覆というのは、様々な茶道具を納める袋だ。 この茶箱、六つのパーツからできている。 上写真はそのサンプル。 左上から、外箱、茶入れ、茶碗。 右下、茶巾、茶筅(ちゃせん)、茶杓(ちゃしゃく)。 外箱と茶入れは赤木氏が作る。 仕上げは「拭き漆」の手法だ。 茶碗はドイツ在住の陶芸家・李英才作。 「茶杓はぱるばさんが竹で作ったら?」と言われたが、ま、それはやめとこ。 仕覆は、外袋から茶杓用の小袋まで、Maki布を使って縫製する。 そこで赤木氏と真木千秋が布を見ながらいろいろ相談しているところ。 様々な裂(れつ)を使って作るのだそうだ。 初の試みだが、さてどんなものができるか。 |
 |
||
 |
|||
黒田泰蔵工房訪問
「十年の絲なみ・其の二」出展の磁器作家・黒田泰蔵さん。
氏には2001年4月、青山で展示会をお願いしている。
昨日(2/7)、東伊豆にある氏の工房を訪ねる。
 う〜ん、スゴい!
う〜ん、スゴい!
周囲から隔絶され、まさに絶海の孤島のごとき趣。
遙かに相模湾を見下ろすリビングにて、久々にいろいろお話をうかがう。
一見とっつきづらい風情だが、興が乗るとヨシモト顔負けの名調子。
さすが道頓堀の血が流れているだけある。
工房に案内され、作品を見せてもらう。
今回の展示会は作家数も多いので、十点ほどと思っていたのだが…。
やっぱり黒田大好きの真木千秋。
実物を目にすると、とても十点にては収まらない。
あれもこれもと手にとっているうち、その数五十を越えてしまう。
右写真はそうして選んだ出品作。
このほかに大き目のものが十点ほどあるが、それはまたご紹介しよう。
ところで、黒田作品には、無釉、有釉、灰釉の三種類ある。
この釉薬に使われているのが柞灰(いすばい)と呼ばれるもので、石灰分の多い柞(イスノキ)の灰。
昨今は入手が難しくなっているという。
タッサーシルクも漢字で書くと柞蚕となる。
柞蚕と柞灰、大本の樹種は違うようだが、なんとなく縁を感じる。















